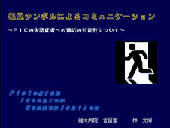
(クリックで拡大)
PIC(ピクトグラム・イデオグラム・コミュニケーション)は1980年にカナダのS.C. Maharajによって主に脳性麻痺児や精神発達遅滞児のために考案された。計約400の具象的なPictogram(絵文字)と抽象的な Ideogram(表意文字)よりなる言語訓練具であり、補助代替コミュニケーション具(Agumentative and Alternative Communication 以下AAC)である。例えば日頃私たちが見慣れた非常口のサインは代表的なピクトグラムである。
本邦へは藤沢ら(1991)によって紹介され、日本の文化に合わせた変更が加えられた後、昨年日本語版PICとして出版された。(図1)
今回、さらに失語症者用にシンボルの追加および利用法の変更を行い、慢性期重度ブローカ失語症者に試行し、実用の可能性について検討した。その利用方法、問題点と限界および将来の可能性について述べたい。

写真1
(写真1.)右がオリジナルのPICボード、左が変更を加えた失語症者用のPICファイルである。主な変更点は
①成人の生活言語という点より約100のシンボルの追加
②シンボルを便宜的に19のカテゴリーに分類(図2)
③ カテゴリー毎に色分けをし、そのカテゴリーを代表するシンボルで見出しをつけファイル化。さらに、ファイルを立てたまま使えるように専用の支持板を作り操作が簡単にできるようにした。
基本的な利用方法は、後に述べる失語症者のメタ認知力の低下の問題より、失語症者が何かを伝えたい様子のときにファイルを差し出し、目的のシンボルを一緒に探し出すという、言わば、レストラン・メニュー方式である。
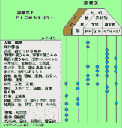
図2 PICカテゴリーと語概念
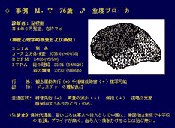
図3 MTさんの概要
T.M 76歳 男性。生活期に入った重度ブローカタイプである。脳梗塞にて平成4年6月に失語症、右片マヒにて発症。損傷部位はブローカ野を中心に弁蓋を含む前頭葉、島、頭頂葉の縁上回まで深部白質を含み広範に広がっているが、側頭葉および縁上回後部から角回は保たれている(図3)。他院で言語および機能回復訓練を10ヵ月間受けた後、当院へ転院。標準失語症検査(SLTA)(図4)では、単語レベルは聴理解、読解ともに100%、短文の理解は共に60%~70%。表出は口頭、書字共に不可能。重度の構音失行、観念運動失行等を伴い、表出面での回復は期待できないと思われた。またWAISの絵画配列は例題を除き困難であった。一方、ジェスチャーの理解や、シンボルの認知は良好で、失語症検査上プラトーに達した一年を過ぎた頃より徐々にPICの訓練を導入した。聴、視覚刺激より目的のピクトグラムのポインティングまで15″~20″と時間を要する時もあるが、約60(オリジナルのボード上)のシンボルを早期に習得、文中の名詞が逆転しても意味が伝わる3語文(非可逆文 例:『看護婦さん/りんご/食べる。』)が絵カードを見て正しい語順でポインティング可能となった。
失語症者による単文の産生に関して、藤田ら(1989)はその文型をレベル1~4(図5)の階層に分けている。この産生力に応じて述べると、選択肢を産生に必要なシンボルだけにした絵カードを見ての文産生においては、レベル4までの受け身文(*印)、使役文以外の文はほぼ正しく産生できた。今のところ「助詞」「受け身」「使役」を表わすシンボルがないこともあるが、いずれにせよ、ブローカタイプにとっての助詞の使用の困難さと、受け身文は能動文で表現可能なことを考慮すると、助詞を削除したいわゆる電文体での意味伝達という目的からは十分であると思われる。同様にレベル4の補文を含む文は難しい。課題時の主な誤りは、述語が主語の次に来るという点と、間接目的語と直接目的語の転置であった。特に前者が頻繁に見られた点は興味深い。
訓練室での自由会話では、筆者は口頭、ジェスチャー、漢字による書字、全てのモードを使い伝達し、Mさんはイエス、ノーとシンボルを指差して答える。元来、気難しい人で、自ら人に働き掛けるタイプではないが、最近は自由会話の中で単語のレベルで自分からPICを差すことが時折見られるようになってきた。
MRI (クリックで拡大)

図4 SLTA 検査結果
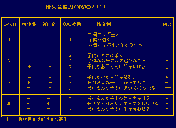
図5 構文産生の階層とPIC
藤田ら(1989)
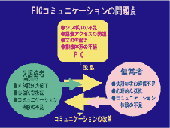
図6 PICコミュニケーションの
問題点
失語症は大きく分けると、Mさんのような理解は良いが表出が困難な非流暢タイプと,理解は悪いが表出は可能な流暢タイプ、および共に困難な混合型タイプがある。どのタイプも原則的には絵の理解は可能であり、非言語的知能、思考力などは保たれている。中でも、非流暢タイプの典型であるMさんのような重度ブローカタイプでは、理解力と表出力に乖離があればあるほど、さらにジェスチャーなどの他のコミュニケーションモードが失行で困難であれば、PICが実際的な手段となりうる可能性は高い。そのためには、以下に述べる問題点にうまく対応して行くことが望まれる。
(1)PICのAACとしての問題点(図6)
第一にPICのコミュニケーション具としての問題がある。まずはシンボルの不足である。小児の場合との相違点でもあるが、成人失語症者は生活体験に基づく獲得概念数が小児の言語障害児とは比較にならないほど豊富である。例えば、小児に必要なシンボルは、『魚』であり、『テレビ』であるが、大人が伝えたいのは『鰹』や『ぶり』であり、『衛星放送の録画番組』であったりする。こうした点を補うためのもっと多数の、同時に分かりやすいシンボルの追加が必要である。しかし、シンボル数の増大は、語意へのアクセスを相対的に難しくする。それを軽減するための工夫の一つとして、理解力の高い失語症者は分類能力も高い可能性(黒田 1994)、また、ブローカタイプはウエルニッケタイプに比べてカテゴライズのパターンは健常者に近い、という点を利用したカテゴリーごとの分類と色分けによるファイル形式が必要である。これは語概念に応じた分類ではなく、いわば日本人の生活体験を考慮した現段階の便宜的な分類であり、カテゴリー間で重複するシンボルがあっても良い。これによって語彙へのアクセスが容易になる。また、家族や知人など各個人の生活に応じた写真やシンボルを十分に増やして行くことが大切である。この語彙へのアクセスの問題は、文レベルの産生と同様に現在急激に普及しているパソコンの利用で大きな改善が期待できる。また、今後は有効な訓練プログラムと教材の開発が必要である。こうした工夫と今後はパソコンを利用した専用のツールの開発により、PICがAACとして利用できるようになれば、ブローカタイプの失語症者の能力障害(disability)はある程度埋められる可能性がある(Kieczewska
1987)と考えられる。
(2)失語症者の側の問題点
これは、機能障害(impairment)の問題であり、脳に損傷を受けた以上ある程度は障害として残ることを受容しなければならない。その障害の中でも、失語とそれに付随しやすい失行以外の問題として、PICに対するコミュニケーション手段としての認知の問題がある。これは、筆者は、その原因に脳損傷によるメタ認知力(三宮
1996)もしくは自己モニタリング力の低下があると考える。つまり、言いたい思いが心に浮かんだとき、伝えたいという思いに意識は支配されてしまい方略(手段)としてのAACの存在は意識に上らない、そのために有効な手段となるはずのAACを利用できないという問題がある。また、多くの刺激の中から目的のシンボルを弁別し、探し出すことは健常者に比べると困難な作業である。もう一つは、機能障害の問題ではなく、心理的な抵抗という問題である。それまでごく普通に話していた失語症者にとって、AACは生得的なコミュニケーション手段では無く、こうした器具を利用することは心理的に違和感が大きいということである。こうした背景より、健常者がPICを差し出すレストランメニュー方式が必要である。
(3)コミュニケーションの当事者としての健常者の側の問題点と対応
最後に、コミュニケーションの相手としての健常者の側の問題がある。まずは失語症に関する理解不足が挙げられる。例えば、ほとんど有効でない仮名50音のボードを使わせようとする場合も珍しくない。また、失語になると家族や周りの人々は一人のコミュニケーションの主体として認識することが難しくなる。そうでなくても失語症者と同様にPICのようなAACの利用に心理的な抵抗が出てくることは想像できる。従い、失語症者の社会的不利(handicap)を埋めるための健常者の側の第一歩は、これはすべての言語障害者について言えることであるが、相手を「伝えたい」思いをもったコミュニケーションの主体として認識することである。その上でPICを使ったコミュニケーションの体験を実生活の中で積むことである。「伝わった」という実感を何度も得させることが必要である。失語症者、健常者が共に持つ心理的な抵抗は体験を積んで行く中でしか減って行かないと考える。私たちは音声言語の獲得にどれだけの時間を掛けたかを思い出す必要があろう。実体験なくしては手段として定着すること、即ち「学習=行動の変容」は難しい。
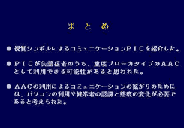
まとめ
近年は手話が社会的にも広がりを見せている。健常者が難聴者のコミュニケーションモードに合わせる『関係論』(宮崎 1986)の時代になってきた。同様に失語症者との対応においても認識を新たにし、失語症者の社会的不利 (Handicap) をうめる手段としてのAACを彼等の前に差し出していく必要があろう。さらに、それにて実際にコミュニケーションをとる場合、鯨岡 (1989)のいう相手の身になり何を伝えたいかを察する態度、『間主観的』態度が必要であろう。この態度があれば、目的のシンボルに達することは可能であり、その結果、相手の気持ちが象徴化されたものとして理解可能となる。
高橋(1991)によれば、失語症者の約半数(53.2%)は重度であり、重度の中でもブローカタイプが一番多い。PICコミュニケーションは重度ブローカを中度にする可能性を持っており、生活言語として機能する可能性を持っている。さらにこの可能性の実現に取組たい。
1)S.C. Maharaj(日本語訳 藤沢ら):「視覚シンボルによるコミュニケーション」 ブレイン出版 1995
2)藤沢和子、井上智義:絵単語によるコミュニケーション 大阪教育大学 聴覚言語障害児教育教「研究紀要」 第13号平成3年3月10日
3) 黒田喜寿:失語症者の非言語性象徴機能障害について 失語症研究 Vol.14. No.2; p147~153 1994.6
4)藤田郁代:失語症者の構文の産生力の回復メカニズム 失語症研究 Vol. 9 No.4, p 237~244 1989. 12
5)三宮真智子:「認知心理学 4」 p157~p180 東京大学出版 1996
6)Kieczewska, M., Carlson, G., Steeele, R., and Heinrich,M.(1987) Patterns of learning in aphasic trained on a computer-based visual communicative system. Proceedings of RESNA10th
Annual Conference, San Jose, California, pp. 157-159
7)宮崎隆太郎:「障害児の意義申し立て」p88~90 三一書房 1986
8)鯨岡 峻:初期母子関係における間主観性の領域 「母と子のあいだ」 p277~312 ミネルバ書房 1989
9)高橋正:重度失語症の出現率、特徴、予後 聴能言語学研究 Vol.8 No.3 、P146~p156、1991
