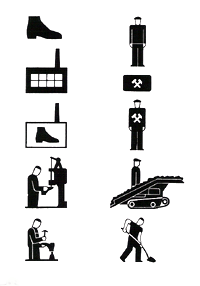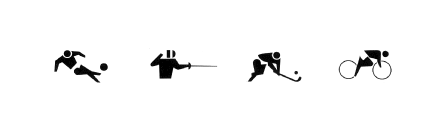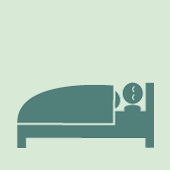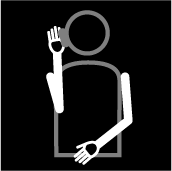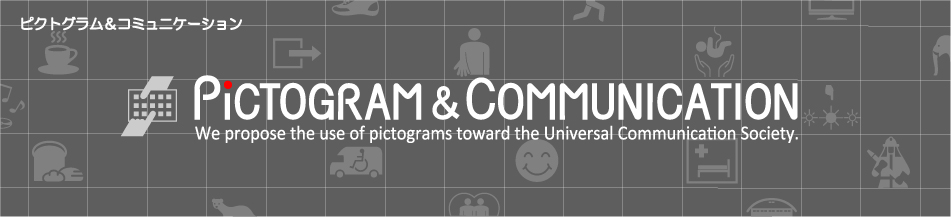 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクトグラムデザイナーの詩*
最初のピクトグラム
「ピクトグラム(pictogram, pictograph)*」は、日本語では「絵文字」や「絵単語」と訳されることがあります。言葉の代わりに「絵」で意味を伝える、視覚的な記号です。 ピクトグラムの起源 ピクトグラムの起源は、はるか昔の壁画にまでさかのぼります。フランスのラスコーやスペインのアルタミラの洞窟に描かれた壁画は、人類最初の「絵による表現」とも言われています。 もしかすると、現代人の祖先であるホモ・サピエンスは、進化の途中で分かれたネアンデルタール人と、こうした壁画を通じてコミュニケーション*を取っていたかもしれません。 これらの壁画に描かれた太陽や牛などの絵は、そこに「実際には存在しないもの」を表し、人々の祈りや儀式の中で、共通の記憶を呼び起こす「しるし(sign)」として機能していたのです。 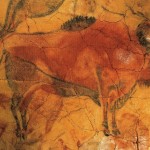 アルタミラの壁画 芸術家デッサン情報HPより よく知られているように、こうした壁画や絵は象形文字*を生み出し、時を経て漢字のような表意文字へ進化しました。一方、永い間人目に触れることのなかった絵による壁画は、あたかもコミュニケーションの道具=「ピクトグラム」として現代に蘇えったように感じられます。 象形文字からピクトグラムへ このような古代の絵は、やがて象形文字を生み出し、時間をかけて漢字のような表意文字へと進化しました。 一方で、長い間忘れられていた「絵によるコミュニケーション」は、現代に入り「ピクトグラム」という形でよみがえり、再び私たちの暮らしの中で大切な役割を果たすようになっています。 ● ● ●
オットー・ノイラートとアイソタイプ ピクトグラムを体系的に使い始めたのは、オーストリアの社会学者・思想家であるオットー・ノイラート(Otto
Neurath)*です。彼は、ウィーンの展示館の企画にあたり、誰にでもわかりやすく情報を伝えるために、「ISOTYPE(アイソタイプ)」と呼ばれる絵記号のシステムを考案しました。
組み合わせによる表現力 アイソタイプでは、「靴」+「工場」=「靴工場」というように、複数の図を組み合わせることで新しい意味をつくり出すことができます。この考え方は、当サイトで紹介しているピクトグラムにも活かされています。 同じ図形を使いまわすことができるのは、ピクトグラムの最大の特徴である「単純化(シンプリフィケーション)」というデザイン手法があるからこそ。シンプルな図形だからこそ、自由な組み合わせと応用が可能になるのです。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案内用サインの歴史 ピクトグラムが日本に広まったきっかけ 日本でピクトグラムが広く知られるようになったのは、1964年の東京オリンピックがきっかけです。
初期のピクトグラムとその反応 競技ごとにシンボル化された斬新なデザインのピクトグラムは、多くの人々の心をひきつけました。
その後、1970年の大阪万博では、トイレの案内サインとして「男女」のピクトグラムが初めて使われました。しかし当初は、これがトイレのマークであることがまだ一般には認識されておらず、「便所」と書かれた紙が横に貼られていたという話*も残っています。 現在では考えられないことかもしれませんが、「ピクトグラムが社会に浸透するには時間がかかる」という事例でもあります。 デジタル時代とピクトグラムの進化 近年では「アイコン(icon)」という言葉がコンピュータ分野を中心に一般化し、多くのデザイナーが様々な種類のピクトグラムやアイコンを作成するようになりました。 デジタル技術やデザインソフトの進歩により、より洗練された、美しいピクトグラムが次々と生み出されています。 見た目の美しさvs ユニバーサルデザイン 1998年の長野オリンピックでは、流線型のスタイリッシュな競技サインが登場しました。グラフィックとしての美しさは際立っていましたが、知的に障害のある方々にとっては、少し複雑で「絵解き」が必要な場合もあったかもしれません。  1998年 長野オリンピック競技サイン
誰もが直感的に理解できることを目指す「ユニバーサルデザイン(UD)」の観点からは、見た目のかっこよさだけでなく、「誰にでも伝わる」ことが大切です。 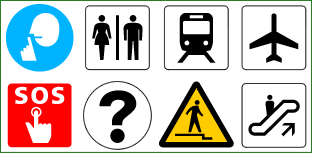 標準案内用図記号例 (交通モビリティ・エコロジー財HPより) ● ● ●
主張しないデザインこそ、良いピクトグラム 良いピクトグラムの条件のひとつは、「目立たない」こと。広告やロゴのように人目を引くのではなく、「必要なときに、自然と目に入ってくる」ことが求められます。 例えば、外出先で急にトイレに行きたくなったとき、普段は意識していない「男女」のマークが、パッと目に入ってきた…そんな経験、ありませんか? このように、ピクトグラムは必要なときに人の意識に上がることで、本来の役割を果たします。これは、生き物としての私たちの「重要な情報を優先的に処理する」仕組みを持っているからでもあります。 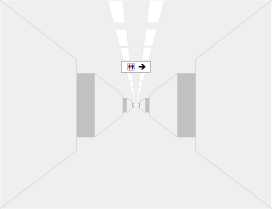 我慢できない!トイレはどこ? 最後に ピクトグラムは「絵」なので、完全に感情や印象と切り離すことはできません。だからこそ、デザイナーは意識的に“主張しないデザイン”を目指すべきなのです。 それは、文字が主張せずに意味だけを伝えるように、ピクトグラムもまた、感情に訴えるのではなく、情報を静かに届ける存在であるべきなのです。 それこそが、アイコン(icon)という記号(sign)の働きなのです。 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ピクトグラムの構造とデザイン
非常口のピクトグラムが生まれた背景 
誰もが目にしたことのある「非常口」のサイン。実はこのサインは、熊本市で起きたデパート火災をきっかけに誕生しました。それまで「非常口」という漢字だけの表示では、緊急時に適切な避難誘導ができないと問題になったのです。そこで一般公募によりデザインが選ばれ、グラフィックデザイナーの太田幸夫氏によって現在の形にまとめられました。 この「走る人」の図は、人物のシルエットや空間のバランス、シンプルさにおいても、ピクトグラムの理想形といえます。
色と視認性の関係 しかし、色彩学の観点からは、視認性の高い色の組み合わせとして「黒地に白図」が上位に位置づけられています。実際、白黒の組み合わせでは「黒地に白図」が3位であるのに対して、「白地に黒図」は7位とされています。そのため、JIS絵記号では、コミュニケーション用ピクトグラムでは、黒い背景に白い図を基本としています。
ちなみに、視認性で最も高いのは「黒地に黄色」であり、これは多くの警告サインに使われています。 ピクトグラムにおける「単純化」と「輝度差」 ピクトグラムは、正方形の地に対し、線ではなく面で構成された図を使うのが基本です。これは、情報をできるだけ簡潔、明確に伝えるため、対象の特徴を削ぎ落とし、面の図形として抽象化する手法です。 視認性を確保するためでもあります。 この「単純化」と「地と図の輝度差」の2つが、ピクトグラムにおいて特に重要なデザイン要素です。色のない記号でありながら、情報を的確に伝えられるのはこの構造のおかげです。 たとえば、白い図は視覚的に浮き上がって見えると感じることがあります。これは、黒と白の光の反射率が約1:16という大きな差によるもので、脳が瞬時に注目する仕組みを生み出します。良質なピクトグラムは、コントラストを最大限にし、見た瞬間に「意味」とつながるよう設計されているのです。視覚野で働く信号の手助けをします。 図形の背景としての「正方形」と「黒」 ピクトグラムにおける背景(地)としての「正方形」や「黒色」にも理由があります。正方形という形は自然界にはあまり見られず、人工的であるがゆえに、「記号である」という存在感を持ちます。黒色は、言わば「闇」。何もない空間に図を浮かび上がらせ、見る者の注意を引きつける舞台装置のようなものです。 このように、ピクトグラムを作るには、単なる図案ではなく、 生理的・心理的な視覚の働きを理解した上での制作が求められます。個人の趣味や時代の流行に左右されない、障害をもつ人を含めた真に「ユニバーサル(誰もが理解できる)」な視覚言語を作る姿勢が重要なのです。 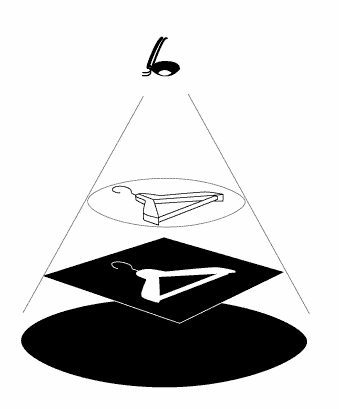 ピクトグラムの心理的な三次元構造 *
ピクトグラムの統一性と「没個性」 ピクトグラムは、あらゆる概念を表すため、数十〜数千という単位で制作されます。そのため、デザインには整合性や統一感が求められます。これは、文字における「フォント」の統一と似ているかもしれません。
たとえば、ゴシック体と明朝体が混在していては読みづらいのと同じで、ピクトグラムでも「揃った印象」が必要です。個性を抑え、主張しすぎず、しかし伝えたい意味は確実に伝える――そんな「最大公約数的な形」を目指すことが、本質的に重要といえるでしょう。
ピクトグラムとは何か つまり、ピクトグラムとは、 確かなな図と地の構造に支えられた、最大多数にとって理解しやすい、視覚的な言語 なのです。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アイコンやサインとの融合 ピクトグラムの広がる活用と、サインやアイコンとの融合 ピクトグラムは、まるで空気のように自然に私たちの周りに存在し、情報を視覚的に伝えてくれる“絵の言葉”です。そのシンプルで直感的な特性のおかげで、さまざまな場面で使われています。 もともとは駅や空港など、公共施設の案内用サインとして広く認知されてきましたが、インターネットの広がりと共にホームページやソフトウェアのアイコン、機器やマニュアル、イベントの案内表示、さらにはユニバーサルデザイン(UD)や情報デザインの分野にまで応用が広がっています。 ■イベント等のサイン: 国際こども図書館(イベント展示利用) 「読書の楽しみをすべての子どもたちに」 ■消防署内のサイン(施設内利用) 
 仮眠室 無線室 (c)Office Slowlife
● ● ●
ピクトグラムは一般にネットなどデジタル世界での「アイコン」としても活躍します 。ピクトグラムは、色や質感の加工を加えても、情報のわかりやすさを保ったままアイコンとして使えます。たとえば: ・元のモノの色を活かせば、より直感的に理解できる. ・ 一度覚えれば、小さく表示しても読み取りやすい ・ 視認性とデザイン性の両立が可能
立体感のあるクールなデザインにも変換でき、小さく表示しても意味が伝わります。下のアイコンは、当サイトのピクトグラムを元に制作したアイコンの例です。 2000年代Windowsのアイコン風に (「時計」302016 「Tシャツ」303013 「救急車」401012) 小さくしても、ピクトグラムは威力を発揮します。単純化を進め彩色した日本の十二支の動物をシンプルに彩色し、並べてみると親しみやすい視覚表現になります。(人・動物>陸の動物104〜空の動物・他106より)  加工をしてもギリギリ理解可能? (「家族」110003) まとめ ピクトグラムを「描くこと」は、情報とデザイン、そして色彩のバランスを意識する訓練にもなります。 まずは、ピクトグラムからアイコンを作ってみる──そんなプロセスから、伝わるデザインが生まれていきます。
デザインの単純化
単純化のレベルと指標
双方向コミュニケーションへの応用 そして今、新しい次元へステップアップする時代がやってきました。これまでの単体での役割から、複数のピクトグラムを使ってのコミュニケ ーション・システムへの利用です。ある意味それはピクトグラムが脇役から主役へシフトする時代とも言えます。 言語にハンディキャップのある人のコミュニケーション手段として、また異文化コミュニケーション、例えば外国でお医者さんに診てもらいたい時に指し示す絵単語として利用ができます。多くの先進国では、ハンディキャップのある人々は社会参加を求めまています。また、世界中で人の行き来とやり取りが増すにつれ、このようなコミュニケーション手段が求められる時代となってきました。 1960年代からは「ノーマライゼーション」、また近年のハンディのある人を社会で包み込むという理念を表した「インクルージョン」という言葉に代表されるように、世界はあらゆる点でハンディのある人と健常者の別を無くす方向に向かっています。UD(Univearsal Design)も同様の理念に立ちますが、これらの取り組みの中で、ピクトグラムはコミュニケーション支援という点で理想的だとと考えます。
そのような目的で、当オフィスの林と(株)高知デジタスタジオさんによって1996年に日本で最初に作られたピクトグラムの例です。 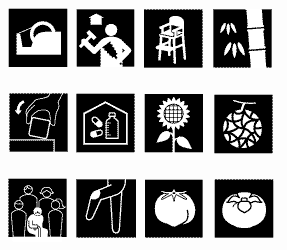 日本版PICシンボル(1998) *
● ● ●
ネットが大きな情報交換ツールとして進化した今、もはやピクトグラムでの人工言語も夢ではないでしょう。下記は当オフィスの代表、林が2010年にその可能性について発表したたものです。 「ピクトグラムを利用した視覚シンボルコミュニケーションシステムの提言」
(2010年 第3回国際ユニヴァーサルデザイン会議発表ポスター) ● ● ● また新しい試みとしては動画があります。場面の理解、知的障害をもつ人の動詞の概念学習などさまざまな利用方法が考えられます。
シンボル研究のための実験的な試みですが、ピクトグラムデザインをベースに発展させたアニメーションで手話(「聞く」)の動きを表現してみました。より記号的なピクトグラムですね。腕と手を白で、身体の輪郭をグレイ線にして、主と背景のように分けて理解し易くしました。 ● ● ●
いかがでしたでしょうか、楽しんで頂けたでしょうか。ピクトグラムの可能性について少しでも理解共感して頂けたら幸いです。 ▼FaceBookページではピクトグラムや人工言語についてのアイディアなどさらに詳しい記事がご覧いただけます。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||